
主婦の方で、少しでも家計の足し、または自身のお小遣いの足しになればとパートをする方も少なくないのではないでしょうか。
しかしながら、配偶者である奥様の103万円の壁、または106〜130万円の壁にとはどのようなものなのか、理解をしておく必要があります。
今回は、パートのお給料と税金の関係性についてご紹介して行きます。パートでの収入を考える上でのご参考になれば幸いです。
1、みんなはどのくらいに抑えてる? パート主婦の平均月収

厚生労働省の毎月勤労統計調査(2017年3月速報時点)によると、パートをしている主婦の平均月収は約95,000円という結果がわかったそうです。2018年3月現在の現在の東京都の最低賃金が1時間932円であるため、月に平均100時間程度働いている計算になることがわかります。
2、所得税と住民税の違いとは?

パートやアルバイトの方が気をつけないといけないのが、「所得税」と「住民税」についてです。
下記では、それぞれについて詳しくご紹介して行きます。
(1)所得税
所得税とは、労働者の所得に応じてかかる税金のことです。
所得税は、「所得控除65万円+基礎控除38万円の合計103万円」を給与から引いた額に対して課税されます。
そのため、一般的に言われる「103万円の壁」=「所得税が課税されるライン」ということになります。
(2)住民税
住民税とは、「都道府県」と「市区町村」に納める税金のことで、納税者の所得に応じて異なる「所得割」と一定額を納める「均等割」の2種類があります。
下記では、それぞれについて詳しくご紹介して行きます。
①所得割
所得割は、収入が「所得控除65万円+基礎控除33万円の合計98万円」未満であるかどうかが課税・非課税のラインとなります。
ただし、納税者に扶養親族がいない場合にのみ、基礎控除額が35万円に設定されます。
そのため、収入が98万円未満(扶養親族がいない場合には100万円未満)であれば税金の支払い義務は一切なく、収入が=手取りになるというわけです。
所得割は、市民税6%・県民税4%の合計10%の税率と決められています。
例として、収入が102万円だった場合の住民税の計算方法は下記の通りです。
(102万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円)×10%=4千円
102万円の収入の方の住民税課税額は4千円という計算になります。
※基礎控除額35万円は、課税・非課税のラインを決めるための基準であるため、実際に計算を行う場合には、基準控除額である33万円での計算となります。
②均等割
均等割は、基本的には全国一律で「県民税1,000円+市税3,000円=4,000円」と定められています。
しかしながら、平成26年(2014年)からの10年間は、東日本大震災の復興特別税として県民税、市税共に各500円(計1000円)が加算されています。
均等割の課税・非課税のラインは、地域ごとに定められた「住民税所得割の課税基準は総所得金額(お住まいに地域によって変わります)」によってそれぞれ決められます。
均等割が課税されるラインは、「3級地区93万円、2級地区96.5万円、1級地区100万円(級地区別非課税基準によって異なる)」となります。
級地区別非課税基準額は、下記の通りです。
1級地の場合→35万円
2級地の場合→35万円×0.9=31.5万円
3級地の場合→35万円×0.8=28万円
という基準設定になっています。
お住いの地域の級地区分に関しては、厚生労働省の「級地区分(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/29kyuchi.pdf)」をご参照ください。
ご自身がお住いの地域の級地区分によって、住民税の均等割の課税・非課税ラインが異なるというわけです。
例えば、お住いの地域が1級地の場合には、「所得控除65万円+住民税所得割の課税基準は総所得金額35万円の合計100万円」以上の収入で均等割が課税。
2級地の場合には、「所得控除65万円+住民税所得割の課税基準は総所得金額31.5万円の合計96.5万円」以上の収入で均等割が課税。
3級の場合には、93万円以上で課税対象。というわけです。
3、手取りが減る!?パートのお給料と税金の相関について

ここでは、収入額別の手取りと税金の相関についてご紹介して行きます。
①年収98万円未満
所得税、住民税の課税はなく、パートで稼いだ収入がそのままの手取り金額となります。
課税義務が発生しないことが、98万円未満の収入のメリットです。
②年収98万円以上~100万円未満
住民税の均等割が発生する地域はありますが、基礎控除額が35万円の地域は、パートでの収入がそのまま手取りとなります。
③年収100万以上~103万以下
年収が100万円以上になると住民税の均等割と一律10%の住民税の所得割が課税されます。
手取りは「年収-住民税」になります。
④年収103万円超~130万円未満
年収が103万円を超えると所得税が課税されます。パートをされている方の中には、このラインを気にして労働時間を計算している方も少なくありません。
所得税は収入額が大きくなればなるほど額が大きくなります。103万円以下は夫の所得税の計算上、配偶者控除を適用することができ、141万円未満の場合で、夫の年収が1千万円以下のとき夫の所得税の計算上、配偶者特別控除を適用することができます。
手取りは「年収-(住民税+所得税)」になります。
⑤年収130万円以上~141万円未満
年収が130万円以上になると夫が会社勤務の場合、社会保険の扶養から外されてしまいます。そのため所得税と住民税に加えて、ご自身で国民年金や国民健康保険、介護保険などの社会保険を支払う必要があります。
また、パート先で社会保険の加入義務を満たした場合、パート先で厚生年金や健康保険、介護保険などの社会保険を支払う必要もあります。
手取りは「年収-(住民税+所得税+社会保険料)」になります。
⑥年収141万円以上
年収が141万円以上になると、完全に夫の所得税の計算上配偶者特別控除を受けられなくなります。
手取りは「年収-(住民税+所得税+社会保険料)」ですが、夫の所得税の計算上配偶者特別控除が受けられなくなってしまうため、年間の収入が141万円以上超えてしまうと、かえって損をすることもあるため、ご家庭での話し合い、注意が必要です。
まとめ
これまでパートのお給料と税金の関係性についてご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
パートをする上で自身に関係する身近なことですが、なかなか知るタイミングがなかったという方でも、パートでの収入を考える上でのご参考になれば幸いです。

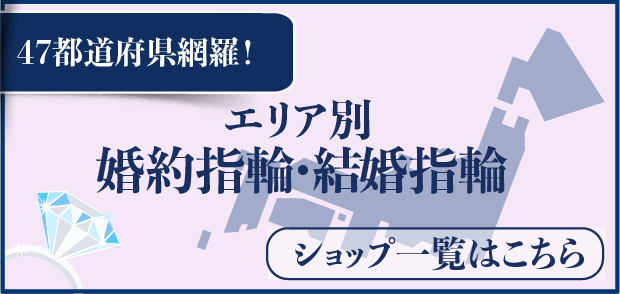
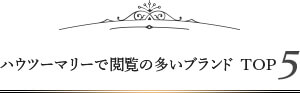













COMMENT
コメント
この記事に関するコメントはこちらからどうぞ
コメントはこちらからどうぞ