
結婚式の準備に追われているとついつい後回しにしてしまいがちな結婚式の二次会の準備ですが、二次会は感動的な結婚式とは対象的に友人たちと盛り上がれる大切な時間です。
しかし、二次会まですべて新郎新婦が準備していては時間がいくらあっても足りませんよね?
では、結婚式の二次会はどの様に準備していけばいいのでしょうか。
ここでは、結婚式の二次会を成功させ、友人たちに楽しんでもらえるための準備の仕方をお教えします。
目次
1.サポートをしてくれる友人を探す

出典:GAHAG
新郎新婦が二次会に多くの時間を割くのはなかなか難しいので、ポイントになってくるのは友人たちのサポートです。
幹事や当日の司会、受付をしてくれる友人を探しましょう。
1-1.幹事
幹事は二次会の成功を左右する大切な役割です。
当日の進行を店側と打合せして決めていったり、時間がない新郎新婦は二次会参加の出欠確認をお願いしたり、当日も何かと動いてもらう二次会のプロデューサー的存在になってきます。
店探しや店との話し合い、当日の進行決めなどたくさんの時間を割いてもらわなくてはいけないため、幹事に選ぶ友人は仲の良さだけで決めるのではなく、しっかりと当日まで幹事を全うしてくれそうな人を選びましょう。
幹事と連携が取れないと、店側も話し合いが進まずに困ってしまったり、当日ぐだぐだになってしまいかねません。
ただ、しっかりとした幹事が見つかっても新郎新婦が忙しいからといって全てを幹事に投げてしまうのはNGです。
ちゃんと店が決まった後も、最初の店との話し合いには同席し、数回の話し合いがあるようなら時間が取れるときは同席しましょう。
結婚式の二次会の幹事はそう何度もするものでもないですし、ほとんどの人が初めてなので金額の大きい話をされてもとまどってしまいますので、お金の話しは幹事ではなく新郎新婦がちゃんと対応しましょう。
幹事が決まったら、自分たちが絶対にやりたいことやできればやりたいことなどあれば伝えておいてください。
その方が店側との話し合いもスムーズにできますよ。
1-2.司会
幹事が決まったら結婚式の二次会当日の司会を誰にお願いするか決めましょう。
できれば幹事と連絡が取れる人が望ましいかと思います。
大体の進行が決まってきたあたりで幹事とともに店側との話し合いに参加してもらえば、進行表を観るだけではなく当日の流れがより把握できます。
幹事と顔見知りならそういった連携も取りやすく、二次会当日に急なトラブルがあったりしても対応しやすくなります。
もちろん幹事と顔見知りでなくても大丈夫ですが、結婚式の当日になる前に新郎新婦が顔合わせさせてあげるといいのではないでしょうか。
新郎新婦も幹事と共に店との話し合いに参加する時に、司会の方にも声をかけて参加してもらえばいいかと思います。
1-3.受付
受付はお金を任せることができそうであれば、大丈夫です。
ただ、大金を預かってもらわなくてはいけないので、責任感の強い方に任せると安心かと思います。
結婚式の二次会当日、来ていない参加者がいると受付の方は二次会が始まり、周りが盛り上がっている時にもしばらく受付にいなくてはいけないことの方が多いので、幹事や司会同様にしっかりとお礼をしましょう。
2.結婚式の二次会会場を選ぶポイント

出典:GATAG
結婚式の二次会ができる会場はとても多く、何をポイントに選んでいいのかわからないですよね。
たくさんある会場をどの様に絞っていけばいいのでしょうか。
2-1.ゲストに配慮した立地
まず最初に店を絞る点は立地条件です。
結婚式から参加するゲストは、正装をし重たい引き出物を持っています。
さらに結婚式でそこそこ飲んで酔っている方もいますので、できるだけ結婚式の会場から離れていない場所が望ましいです。
電車移動で乗り換えがなく、数駅程度の範囲で絞ったほうがいいでしょう。
2-2.参加者予定人数と会場の広さ
結婚式場周辺で会場を絞ったら、次に二次会に参加予定の人数を確認し、人数に見合った広さのお店に絞ります。
狭いのはもちろんですが広すぎても会場貸切の最低保証料金がその分高額になるので、ちょうどいい広さのお店を探しましょう。
例えば、予定人数が50人なら「最大80名まで可能」としている会場だったり、80〜100名くらいなら「最大120名まで可能」としている会場を探すといいのではないでしょうか。
最大人数は、立食か着席かでも変わってきますので、立食か着席かもここで決めておくといいかと思います。
ただ完全な立食はゲストが疲れてしまいますので、みんなでわいわい楽しみたいから立食にしたい場合も、疲れた時にちょっと座るスペースがあるような半立食スタイルがおすすめですよ。
そういった要望は、最初の電話での問い合わせの時に可能か確認しておきましょう。
2-3.会場スタッフの対応
いくつかの会場に絞り、希望の日時が空いていたら次は会場見学です。
その時にしっかりと見ていただきたいのが、スタッフの対応です。
見学予約して来た新郎新婦に見学の案内をする準備をしっかりしてくれているか、色々な質問にしっかりと答えてくれるかなど当日もこの人達なら任せられると感じた会場をぜひ探してください。
見学の段階で確認しておくことは
・最低保証金額
・コースの金額と料理やドリンクの内容
・クロークの有無
・当日の会場(テーブルの置き方など)のイメージ
・無料のオプションと有料オプションの内容
・持ち込んだ音源や映像を流せるか
・当日までの打ち合わせ回数や流れ
最低でも上記の内容は確認しておきましょう。
打ち合わせを全くしない店もありますので、いい二次会にしたいならしっかりと打ち合わせをしてくれる会場を選ぶことをオススメします。
3.結婚式二次会のタイムテーブルの作り方
二次会の会場が決まればいよいよ当日の内容決めです。
進行表を会場側に作ってもらうか、自分たちで作成して話し合いのたびに持参するようにしましょう。
タイムテーブルを作る時の注意点はどのような点なのでしょうか。
3-1.イベントを盛り込みすぎない
イベントとは、新郎新婦によるケーキカットなどの演出や余興やゲームの事です。
ゲストに楽しんでもらいたい気持ちから、あれもこれもとなってしまいがちですが、あまりに色々盛り込みすぎると歓談時間が短くなり、新郎新婦と写真を撮ったりすることもできなくなってしまいます。
ゲストも落ち着いて食事することができず、慌ただしくなってしまいますよ。
3-2.歓談時間を長くしすぎない
ゲストとアットホームな雰囲気で盛り上がりたいから、余興やゲームをなくして全部歓談時間にしよう!と思っている方もいるかもしれません。
しかし何もないまま歓談時間がだらだらと続いてしまうと、ゲストも飽きてきてしまいます。
仲のいい友達がたくさん参加しているゲストはいいかもしれませんが、2、3人の少人数参加のゲストは長い歓談時間は肩身が狭くなってしまうかもしれません。
会場の雰囲気をだれさせないためにも、所々でちょっとしたイベントを挟むといいかと思います。
歓談時間は長くても短すぎてもあまり良くなく、貸切時間によっても変わってくるので、会場に相談しちょうどいい時間を設定しましょう。
3-3.入場に関して
受付をした後に、ポラロイド撮影をして、一言ポラロイドにメッセージを記入というのはよくありますね。
新郎新婦にとって記念になりますし、やりたいという方も多いのではないでしょうか。
このような、受付の後に何かを書いてもらうなどは、受付の横などでやろうとすると大変な混雑になりゲストの入場だけで時間が押してしまう可能性があります。
メッセージや、手書きするタイプのビンゴカードなどを記入して貰う場合は、各テーブルに予めペンやポスカを置いておくと、混雑が避けられますのでオススメです。
4.ゲームについて

出典:ぱくたそ
結婚式二次会といえば、ゲームがあるのが定番ですよね。
やはりビンゴゲームが今でも主流なのですが、人とは違うゲームをやりたいと考える新郎新婦も多いのではないでしょうか。
4-1.オリジナルすぎない方がいい
自分たちが考えたゲームを!と意気込んで、そのオリジナルのゲームを当日行う前に注意したい点があります。
まず、結婚式の二次会でゲームを行う段階はほとんどの人がお酒を飲んでいます。
結婚式から出て、結構飲んでいる人もいたりしますよね?
そういった人に当日マイクで説明して、一発で理解ができるのかということきちんと考えましょう。
次に、あまりゲストを一斉に移動させるようなゲームは避けたほうがいいかと思います。
ビンゴでさえやらないゲストも必ずいるので、全体を動かそうとしてもなかなか思い通りに動いてくれないと思っておいたほうがいいでしょう。
4-2.ゲームは1回がオススメ
かなり稀ですが、ゲームを2回やるという二次会があります。
しかしゲームは結婚式二次会の最大の盛り上がりの場なので、その盛り上がりを2回やってしまうとゲストが疲れてしまうので、ゲームは1回がオススメです。
ゲストに楽しんでもらえる【結婚式の二次会】にするための会場選びや準備の仕方まとめ
実は今回の内容は、私自身が結婚式の二次会をやる会場でパーティーの担当をしていて、経験したことを踏まえて書いたものです。
たくさんの結婚式二次会を担当させていただき、こういう風に準備したら良くなるのではないだろうかと考えて書きました。
この記事が結婚式二次会会場探しや、進行決めなどに役立ちましたら幸いです。

「HOW TO MARRY」編集部です。ブライダル事業に10年以上携わってきた編集チームが集結し記事執筆+編集しています。業界のノウハウのみならず、すでに結婚という大きなイベントを終えた編集チームの体験を活かし、皆様に最高に幸せな結婚をして頂くべく信憑性のある情報提供を目指しHOW TO MARRYというメディアを運営しています。サイト運営者情報はこちら。


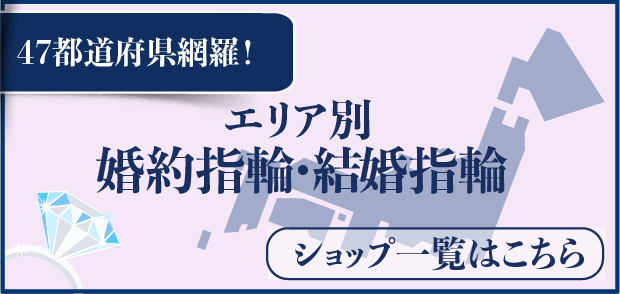
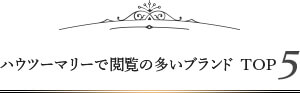













COMMENT
コメント
この記事に関するコメントはこちらからどうぞ
コメントはこちらからどうぞ